| (1) |
事業所数の推移 |
| |
総務省「事業所・企業統計調査」により「理容業」の事業所数の推移を見ると、平成18年調査においては平成8年次対比93.7%となり、規模の大小を問わず、依然として減少傾向が続いている。 |
|
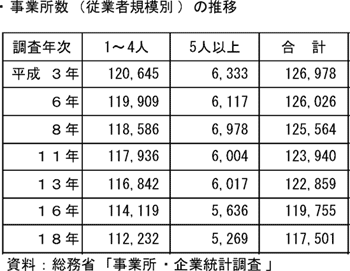 |
|
|
|
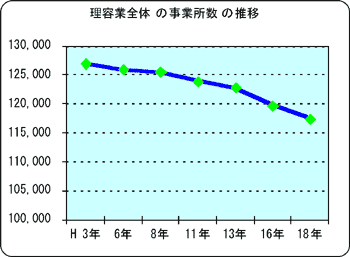 |
| (2) |
施設数、理容師数、免許交付数の推移 |
|
厚生労働省「衛生行政報告例」により「理容業」の施設数、理容師数、理容師免許の交付数の推移をみると、施設(店舗)数は減少傾向が続いている。
免許交付数の減少は著しく、新たな技術者の参入が激減してきている。
・施設数、理容師数、理容師免許交付数の推移
年次
|
施設数
|
理容師数
|
免許交付数
|
昭和45年
|
136,116
|
265,248
|
15,273
|
60年
|
144,939
|
249,206
|
4,935
|
平成元年
|
144,522
|
251,298
|
5,536
|
5年
|
142,619
|
250,858
|
4,467
|
10年度
|
142,786
|
251,859
|
4,651
|
15年度
|
140,130
|
251,981
|
3,250
|
17年度
|
138,855
|
250,407
|
2,727
|
18年度
|
137,292
|
248,494
|
2,559
|
19年度
|
136,768
|
246,861
|
2,480
|
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」
|
| (3) |
最近の業界動向 |
| ア |
大手資本による低料金営業の拡販 |
| |
事業所数の減少幅は施設数の減少幅よりも大きい。一般の理容所は単一施設(店舗)が主体であることから、大手資本のチェーン展開する低料金店舗が大都市のみならず主な地方都市にも進出しているといえる。集客力の高い低料金店舗の拡大は、高齢化社会でのニーズを吸収して、理容業の経営環境を著しく変化させている。 |
| イ |
若年層の理容所離れ |
|
中学・高校生を中心とする10代、更に20代・30代の若年層においては、従来型の「伝統的な理容店」を利用しなくなってきて、明るく開放的なポップスやジャズの流れる美容サロンを利用することが多くなっている。若年需要者のニーズ変化が著しく、「散髪からヘアーカットへ」の流れが定着してきている。 |
| ウ |
後継者の不足 |
|
理容所は、家族を中心とした労働集約型の産業構成によって維持されてきたと言える。この間、理容師免許の交付数は年を追う毎に減少してきており、理容師のなり手が減少している現実は、将来において物理的な後継者不足をもたらしかねない。自信を持って事業の本質を語り、業界全体で後継者の育成に取り組むことが求められる。 |
|
|
2 理容業の特性と現状
| 全国理容生活衛生同業組合連合会による「理容統計年報(平成19年8月調査)」から、業界の現状を探ってみたい。調査時点は平成18年3月末で、組合員を対象としている。 |
| (1) |
個人経営が9割 |
|
90.7%が「個人経営」で、「法人経営」は5.0%にすぎない。税務申告は青色申告が79.6%であり、一方で、白色申告が14.6%を占める。 |
| (2) |
自己所有店舗での営業が7割 |
|
土地・建物ともに自己所有での営業が70.5%を占める。店舗の立地は、「街の周辺地」が41.4%、「郊外」が18.9%、「街の中心地」は18.5%である。 |
| (3) |
10坪前後の店舗で椅子2〜3台 |
|
店舗の広さは「7〜10坪未満」が32.2%、「5〜7坪未満」22.3%、「10〜15坪未満」21.3%が中心であり、設置椅子の台数は「2台」が39.8%、「3台」が35.8%となっている。 |
| (4) |
営業時間は1日に「10〜11時間」 |
|
1日当たりの営業時間は「11時間台」28.8%、「10.5時間台」24.4%、「10時間台」24.0%となっており、10〜11時間の長時間営業である。開店時刻は8時〜9時、閉店時刻は19時が中心となっている。 |
| (5) |
9割以上が固定客 |
|
来店客の固定率は、「90〜95%」が37.5%、「96%以上」32.5%であり、「80%以上」で9割を占める。女性客比率は「1〜5%」48.6%が大半を占め、殆どが男性客の利用で占めている。 |
| (6) |
従業員は店主を含め平均2.2人 |
|
「2人店舗」が44.7%、「1人店舗」が27.0%であり、平均では2.2人となっている。雇用従業員の平均は2.5人で、専従者ありは54.6%を占める。 |
|
|
3 「理容師法」に定める規則等
| 理容業は人の頭髪を施術することから、高度の衛生施設の維持・向上が要求され、昭和22年12月法律施行の「理容師法」が定められている。 |
| (1) |
理容・理容師の定義 |
|
理容とは「頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により容姿を整えること」と定義され、整髪に付帯する仕上げ行為としてコールドパーマネントや染毛等も理容行為に含まれるとしている。
理容師は「理容を業とする者」と定義され、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を受けることを義務付けている。理容師免許を持たない者が理容を業としてはならないとされており、ここで定める「業」とは、反復継続の意思をもって理容を行うことであり、有料・無料を問わない。
|
| (2) |
理容師免許 |
|
理容師免許は、高等学校を卒業した者が厚生労働大臣の指定した理容師養成施設において、昼間課程及び夜間課程にあっては2年以上、通信課程にあっては3年以上の所定の学科、実習を履修した後、理容師試験に合格した者に交付される。
ただし、精神機能の障害により理容師として適正に業務を行うに必要な知識、判断及ぶ意思疎通が適切に行えない者は免許を交付せず、また免許の取消しすることができるとし、また、伝染性の疾病で就業が適切でない場合、業務停止を命ずることができるとしている。
|
| (3) |
理容所(理容を行う施設) |
|
理容師は、理容所において理容を行うものとしている。ただし、病気等により理容所に出向けない者や婚礼等の儀式に参列するため直前に理容を行う場合、その他都道府県知事が認可した場合には出張して理容ができるとして例外を認めている。なお、出張専門の理容師にあっても、施術対象者が当該条件を満たしている限りにおいて出張による理容を可能としている。
理容所を開設または廃止する場合、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出を義務付けている。また、理容所は、届出先の長による使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。 |
| (4) |
管理理容師配置の義務 |
|
理容師の複数存在する理容所の開設者は、当該理容所の衛生管理の責任者として「管理理容師」を配置することとしている。管理理容師の資格は、理容師として3年以上の従事経歴を有し、かつ都道府県知事の指定した講習を修了した者と規定している。 |
| (5) |
環境衛生監視員による検査 |
|
理容師が理容を行う場合、理容師法に定める衛生基準を遵守して運営しているか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は環境衛生監視員を設置し、当該監視員等から報告を求めることとしている。また、監視員は必要に応じて施設等への立入検査ができる。 |
| (6) |
閉鎖命令 |
|
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じて理容所の閉鎖を命ずることができる。 |
|
|
4 理容業界よもやま
| (1) |
進む経営者の高齢化 |
|
厚生労働省の委託で全国生活衛生営業指導センターが実施した「平成17年度生活衛生関係営業経営実態調査(理容業)」によると、経営者の年齢階層では「60歳台」が46.9%で最も多く、次いで「50歳台」30.7%、「40歳台」8.6%、「70歳以上」8.0%の順となっている。60歳以上で54.9%、50歳以上では85.6%を占め、経営者の高齢化は顕著に進展している。理容師免許の交付も減少しており、後継者難は深刻さを増している。 |
| (2) |
経営上の問題点、過当競争が浮き彫り |
|
上記「平成17年度経営実態調査」から経営上の問題点(複数回答)を見ると、「客数の減少」が90.8%で最も多く、次いで「競合店舗の新規出店」33.2%、「客単価の減少」31.2%の順となっている。低料金で多店舗展開する新規参入によって、過当競争の状態にあることが窺える。 |
| (3) |
清潔感があって、技術が熟練 |
|
全国理容生活衛生同業組合連合会「全理連情報」No.54
では、女性利用者の動向調査(平成19年8月)を行っており、興味深い。女性(主婦が50%)が理容店を選択するイメージは、「清潔感がある」50.8%、「技術者が熟練」33.7%の順となり、目的の1位は「シェービング」となっている。男性のニーズと大きな差はないが、期待が大きい反面、一部に不満もあるようである。女性が理容店を利用する選択肢は少ないものの、理容店側にも女性客の扱いに不慣れな側面も垣間見える。需要が存在する限り、女性客開拓を考える必要がある。 |
| (4) |
理容店の利用間隔は5週間に1度 |
|
上記「全理連情報」において、男性の理容店の「利用間隔」を調査している。「5週間」37.8%で最も多く、次いで「6週間」16.3%、「9週間」13.3%の順となっており、約半数が5〜6週間に1度の割合といえる。単純計算では年間10回程度になるが、高齢化社会の進展とともに間隔は長くなって、経営上の問題点「客数の減少」がますます大きくなる。 |
| (5) |
家計調査による「理髪料」支出は減少続き |
|
総務省「家計調査年報」による世帯当たり年間「理髪料」家計支出は、平成18年で6,148円となり、平成12年8,069円、平成15年7,149円に比較して年々減少してきている。
また、世帯主の年齢階層別の支出額を見ると、「70歳以上」が8,627円で最も多く、次いで「60歳台」と続き、年齢層が低くなるにつれて支出は少なくなる。家計支出額を見ても、業界を取り巻く環境変化が浮かんでくる。
|
| (6) |
経営上のポイント |
|
社会生活の変化や顧客ニーズを的確に把握し、低料金で多店舗展開する新規参入に対して差別化を図ることが重要といえる。厚生労働省「理容業の実態と経営改善の方策」から、経営のポイントを探ってみたい。 |
| ア |
顧客ニーズの変化を率直に認識し対応策を構築する |
|
・混雑の予想される曜日に「予約制」導入
・性別、年齢階層別に、仕切りまたは個室など「コーナー」の設置
・洗髪剤の選択、頭皮マッサージ、育毛相談など「高度化サービス」の提供
・出張サービス、介護理容資格など高齢化社会に対応したきめ細かな対応
|
| イ |
サービス面の充実 |
|
・メンバーカードの導入による顧客の固定化
・喫茶コーナーの設置
・PCによる顧客特性の一元管理、迅速で正確なサービスの徹底
・従業員教育の徹底
|
|
|
資料
1 総務省「事業所・企業統計調査」
2 総務省「家計調査年報」
3 厚生労働省「衛生行政報告例」
4 厚生労働省「理容業の実態と経営改善の方策」平成18年10月
5 厚生労働省「平成17年度生活衛生関係営業経営実態調査(理容業)」
6 全国生活衛生営業指導センター「生活衛生関係営業ハンドブック2008」
7 全国理容生活衛生同業組合連合会「全理連情報」
8 全国理容生活衛生同業組合連合会「理容統計年報」
|