| (1) |
事業所数の推移 |
| |
総務省「事業所・企業統計調査」により事業所数の推移を見たいところであるが、同省の統計が「日本標準産業分類」に準拠することから、必ずしも「生活衛生関係営業」と明確に区分が一致しないことを前提に、限定的に見てみる。
事業数として、映画館は減少してきているが少数精鋭化ともいえる。劇場、劇団、演芸などを含む興行場は、このところ増減は一進一退といえる。
|
|
 |
|
|
|
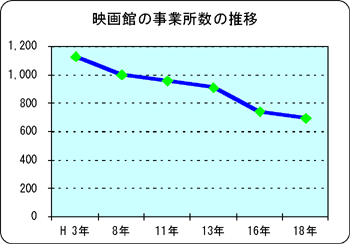 |
| (2) |
施設数、美容師数、免許交付数の推移 |
|
許認可を要する生活衛生関係営業としての「興行場」の動向は、厚生労働省「衛生行政報告例」による施設数の推移によって把握するのが最も正確であろう。
映画館について見ると、昭和35年に7,457施設(館)のピークを迎えたものの、以降テレビの普及とともに大幅な減少を見た。平成6年に2,000施設を割り込み、現在に至っている。
・興行場施設数の推移
年次
|
映画館
|
スポーツ施設
|
その他
|
合 計
|
昭和45年
|
4,480
|
283
|
1,147
|
5,910
|
50年
|
2,696
|
301
|
1,292
|
4,589
|
60年
|
2,451
|
312
|
1,769
|
4,532
|
平成元年
|
2,220
|
324
|
1,962
|
4,506
|
5年
|
2,010
|
350
|
2,227
|
4,587
|
10年度
|
1,938
|
383
|
2,703
|
5,024
|
15年度
|
1,822
|
401
|
2,809
|
5,032
|
17年度
|
1,839
|
387
|
2,808
|
5,034
|
18年度
|
1,815
|
384
|
2,802
|
5,001
|
19年度
|
1,761
|
392
|
2,834
|
4,987
|
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」
|
| (3) |
最近の業界動向 |
| ア |
テレビ放送網が映画製作 |
| |
映画制作と配給はこれまで、専門会社が複数存在して互いに競争してきたが、「日活」「東映」「松竹」は縮小・廃業し、今は「東宝」のみが残って寡占状態にある。この中にテレビ放送網が映画製作を手掛け、テレビ放映と配給において変化が起こってきている。しかし、制作・配給側とユーザーである映画館との関係は未だ従前の形態が残り、映画館側の隷属的な力関係は今のところ大きくは変わっていない。 |
| イ |
映画館の営業収支は上映作品次第 |
|
「黒澤明」「今村昌平」など一時代を画した監督は、その作品で興行が成立した。今は欧米で名声を得る「北野武」であるが、興行収支面では及ばないという。興行収入面で見ると「宮崎駿」ということになる。文芸作品等は姿を消し、アニメーション作品が興行集客力の中核となっている。依然として、映画館の営業収支は上映作品によって左右され、映画館自体の経営努力のみでは成り立たない。
|
| ウ |
平成17年度映画封切り本数731本 |
|
時事映画通信社「映画年鑑」、レジャー白書などを参考に、平成17年度の興行場(映画館)の事業規模を見ると、興行収入1981億円、一人当たり年間映画館入場1.2回、年間封切公開731本(邦画:375、洋画:356)であった。
複合商業施設に併設された「シネマコンプレックス」の増加を背景に、減少を続けてきた映画館入場者数は、増加に転じてきている。
|
|
|
2 興行場(映画館)の特性と現状
厚生労働省の委託により全国生活衛生営業指導センターが実施した「平成18年度生活衛生関係営業経営実態調査(映画館)」から、興行場営業のうち「映画館」について、その現状等を見たい。
|
| (1) |
新たな業態の映画館 |
|
映画館は、密閉性の高い暗黒状態の施設を不特定多数の利用者に供する「暗闇の中での閉鎖型施設」といえる。この施設の形態は変わらないものの、「単独館」が主体であった業態から、大型商業施設に併設する「シネマコンプレックス」等の新たな業態に衣替えしている。
・シネマコンプレックス
映画館1施設内に複数のスクリーンを設置し、複数の映画を同時に上映できる。
10スクリーンを有する施設が約30%、7スクリーン以上が80%を占める。
・マルチシアター
敷地内に複数の映画館を集積して設置し、各館それぞれが映画を上映する。
・ミニシアター
観客席数が300席以下の映画館で、芸術性などに特化した作品を上映する。
|
| (2) |
単独館等の経営者高齢化 |
|
単独館及びミニシアターについて経営者の年齢構成を見ると、50歳以上が計75.3%であり、そのうち70歳以上が26.9%を占める。高齢化が進展しているが、60.2%は後継者ありとしている。
|
| (3) |
営業店舗は借用が過半 |
|
営業店舗の土地・建物については「借用」が53.2%を占める。営業形態が、大型商業施設に併設する「シネマコンプレックス」が主流となってきていることから、この傾向は今後も増加が予想される。
|
| (4) |
観客席数はシネマコンプレックス1500席
|
|
経営形態別の観客席数では、シネマコンプレックス(シネコン)1,530席、単独館424席、ミニシアター193席となり、圧倒的にシネコンが収容能力を誇る。
|
| (5) |
経営上の問題点、「客数の減少」 |
|
経営上の問題点は「客数の減少」が61.1%と突出しており、「施設・設備の老朽化」38.1%、「客単価の減少」31.7%、「人手不足・求人難」21.0%が続く。
|
|
|
3 「興行場法」に定める規則等
興行場営業は娯楽の一環として多数の人が集まることから、適正な衛生水準にある施設の維持・向上が要求され、昭和23年7月法律施行の「興行場法」が定められている。
|
| (1) |
興行場の定義 |
|
興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されている。
興行場法の適用を受ける施設について、「日本標準産業分類」(総務省)によって例記すると次のとおりである。
|
| ア |
映画館 |
| |
アトラクションの有無にかかわらず、商業的に映画の公開を行う事業所をいう。
|
| イ |
劇場 |
|
演劇を提供する劇場及びその付属の劇団、歌劇団、オーケストラ並びに劇場を持つ興行団をいう。主として劇場を賃貸する事業所を含む。 |
| ウ |
興行場 |
|
落語、講談、野球、相撲などの娯楽を提供する興行場及び興行場を持つ興行団をいう。寄席、演芸場、野球場(プロ野球興行用)、相撲興行場、見世物小屋等。 |
| (2) |
法律適用の範囲 |
|
具体的に興行場法の適用を受ける興行場は、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場(プロ野球興行用)、見世物小屋等の施設である。なお、業として映画等の上映を行わない場合は同法の適用は受けない。ここでいう「業」とは反復継続の意思をもって行われることで、公序良俗に反しない社会性は必要であるが、営利性は必要でない。
企業の福利厚生施設として映画上映室を設けるなどの場合のように無料であっても適用を受けるものがある。なお、集会所等であっても概ね月に5回以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となる。カラオケボックスのように本人が歌うことを目的とした施設は興行場ではなく、ビデオ鑑賞ボックスのように機器の操作が店員か顧客かを問わない施設は興行場となる。
|
| (3) |
営業の許可 |
|
業として興行場を営業するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。
興行場の許可は、都道府県の条例で定める構造設備基準に準拠していることが要求され、その運営は都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。
|
| (4) |
環境衛生監視員による検査 |
|
興行場が条例等に定める衛生基準を遵守して運営しているか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は環境衛生監視員を設置し、当該監視員等から報告を求めることとしている。また、監視員は必要に応じて施設等への立入検査ができる。
|
| (5) |
営業許可取消または営業停止 |
|
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、興行場として都道府県の条例で定める構造設備基準または衛生基準に反している場合、許可の取消、または営業停止を命ずることができる。
許可の取消等の処分を行う場合、公開による聴聞会を開催する。
|
|
|
4 興行場の業界よもやま
| (1) |
広辞苑「映画」とは |
|
辞書「広辞苑」で「映画」は“長いフィルム上に連続して撮影した多数の静止画像を、映写機で急速に(普通1秒間に15こま以上の速度)順次投影し、動きのある画像として見せるもの”とある。この定義は最早「風前の灯」であり、近い将来校訂せざるを得なくなろう。
|
| (2) |
デジタル化の波 |
|
映画製作は撮映/現像・加工/配給・上映の3工程によって成り立っている。フィルム世界の仕組みは完成しており、技術上の大きな変化はなかったが、1999年ジョージルーカス監督が一石を投じて以来、業界全体を巻き込む変化の兆しが大きく芽生えている。上映システムの設備投資に課題があり、デジタル技術の革新とともに、シネマコンプレックスの動静が気掛かりである。画質面では実用レベルにあり、上映システムのコストダウンや海賊版防止の技術開発など普及に関する条件が整えば大きく進展する可能性が高い。しかし、観客は技術ではなく映画のコンテンツ(作品内容)を見に来ていることを忘れてはならない。
|
| (3) |
世帯当たり「映画・演劇等入場料」家計支出は、一進一退 |
|
総務省「家計調査年報」により世帯当たり「映画・演劇等入場料」家計支出を見ると、平成15年5,830円、16年6,320円、17年6,655円、18年6,029円と推移しており、一進一退の状態にある。
世帯主の年齢階層別に支出額を見ると、「40歳台」7,159円が最も多く、次いで「50歳台」6,559円、「60歳台」6,079円と続く。40歳台世帯には小学生子弟の居ることも支出の要因と推定されるが、中高年には観劇の機会を望む層の存在が見込まれそうである。
|
| (4) |
経営上のポイント |
|
映画館数、入場人員、興行収入ともに昭和33年前後をピークに、以降大きく減少が続き、ようやく平成9年になって反転したかに見える。減少の要因はテレビの一般家庭への普及、ビデオ関連産業の拡充、娯楽の多様化など、様々な要件の複合的影響を受けたことによると指摘されるが事実であろう。反転要因の大きな1つは、「シネマコンプレックス」の出現と拡大であろう。経済産業省「特定サービス産業実態調査」で、立地環境別に映画館の増減を調査しているが、増加しているのは「ショッピングセンターなどの同居ビル」のみであり、「シネマコンプレックス」がその主体であることが窺える。厚生労働省「興行場営業(映画館)の実態と経営改善の方策」から、経営のポイントを探ってみたい。
|
| ア |
経営環境の変化への対応 |
| |
デジタル技術の発達もあり、変化する顧客ニーズに的確に対応する。
|
| イ |
営業施設の改善 |
|
利用者の快適性を更に追及するとともに、飲食など付随的なサービスの拡充を図る。 |
| ウ |
地域との共生 |
|
地域まちづくりに参画するなど、地域との共生を打ち出す。 |
| エ |
情報化戦略の推進 |
|
情報通信技術を利用した情報提供、予約管理、地元媒体への広告、経営管理を推進する。 |
|
|
資料
1 総務省「事業所・企業統計調査」
2 総務省「家計調査年報」
3 厚生労働省「衛生行政報告例」
4 厚生労働省「興行場営業(映画館)の実態と経営改善の方策」平成19年12月
5 厚生労働省「平成18年度生活衛生関係営業経営実態調査(映画館)」
6 全国生活衛生営業指導センター「生活衛生関係営業ハンドブック2008」
7 日本映画製作連盟「日本映画産業統計」
8 時事映画通信社「映画年鑑」
|