| (1) |
事業所数、施設数の推移 |
| |
総務省「事業所・企業統計調査」により事業所数の推移を見ると、全体として減少傾向が続いており、特に従業者数1〜4人の小規模事業所の減少の幅が大きい。
厚生労働省「衛生行政報告例」による施設数の推移を見ると、第2次大戦後、増加を続け、市民生活の中にその地歩を築いてきたが、平成に至ってからは一進一退の状況に転じ、平成9年をピークとして以降、減少傾向になっている。
|
|
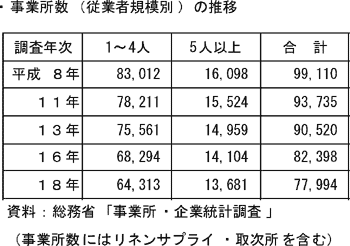 |
|
|
|
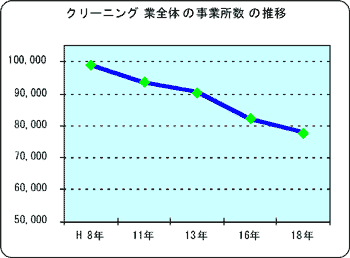 |
|
|
|
・クリーニング施設数の推移
年 次 |
合 計 |
一般洗濯業 |
リネンサプライ |
取 次 所 |
無店舗取次所 |
昭和45年 |
79,183 |
53,927 |
1,661 |
23,595 |
− |
50年 |
96,984 |
55,771 |
2,909 |
38,304 |
− |
55年 |
116,968 |
56,546 |
1,611 |
58,811 |
− |
60年 |
139,342 |
54,459 |
1,599 |
83,284 |
− |
平成元年 |
155,785 |
52,082 |
1,897 |
101,806 |
− |
5年 |
156,068 |
49,621 |
1,608 |
104,839 |
− |
10年度 |
163,999 |
46,319 |
1,784 |
115,896 |
− |
15年度 |
155,109 |
41,866 |
2,175 |
111,068 |
− |
16年度 |
150,753 |
40,431 |
2,233 |
108,089 |
− |
17年度 |
147,132 |
39,375 |
2,360 |
105,134 |
263 |
18年度 |
143,699 |
36,749 |
3,599 |
103,061 |
290 |
19年度 |
140,823 |
36,669 |
2,596 |
101,191 |
367 |
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」 |
| (2) |
クリーニング師、免許交付数の動向 |
|
従業クリーニング師数は、6万人台を割り込む状況になっており、年間の免許交付数については、おおむね1000件程度で推移している。
・従業クリーニング師数、免許交付件数の推移
年 次 |
クリーニング師 |
免許交付数 |
昭和45年 |
79,959 |
2,370 |
50年 |
92,894 |
1,858 |
55年 |
78,321 |
1,228 |
60年 |
75,555 |
1,077 |
平成元年 |
73,678 |
1,563 |
5年 |
71,749 |
1,658 |
10年度 |
69,964 |
1,291 |
15年度 |
65,796 |
1,059 |
16年度 |
63,750 |
1,138 |
17年度 |
61,682 |
1,008 |
18年度 |
61,545 |
1,002 |
19年度 |
59,856 |
1,031 |
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」 |
| (3) |
最近の業界動向 |
| ア |
小規模事業体の減少 |
| |
クリーニング業の事業所数は減少傾向が続いている。総務省「事業所・企業統計調査」によっても、従業者数1〜4人規模の減少割合が高く、個人法人別企業数の推移を見ても個人企業の減少幅が大きい。クリーニング需要の後退の中で、小規模企業の整理淘汰が進んでいるといえる。 |
| イ |
取次店の減少 |
|
厚生労働省「衛生行政報告例」による施設数の推移を見ると、これまで増加を続けてきた「取次店」が平成13年度以降減少に転じ、直近においてもその減少傾向が続いている。
|
| ウ |
「洗濯代」家計支出に下げ止まり感 |
|
総務省「家計調査年報」により1世帯当りの「洗濯代」年間家計支出(総世帯)に見ると、平成17年8,403円、18年7,753円、19年7,872円と推移している。サンプル調査であり限界はあるが、支出減少の下降幅にいささかの下げ止まり感が窺える。バブル末期の平成4年当時に支出ピークを迎えたが、55%を超える減少は業界にとって極めて厳しい現実である。
|
|
|
2 クリーニング業の特性と現状
| 厚生労働省の委託により全国生活衛生営業指導センターが実施した「平成17年度生活衛生関係営業経営実態調査(クリーニング業)」から、「一般クリーニング所」の現状を探ってみたい。 |
| (1) |
高齢化する経営者 |
|
経営者を年齢階層別に見ると、「60歳台」が52.8%で最も多く、次いで「50歳台」21.7%、「70歳以上」13.3%に順となっている。60歳以上の経営者は66.2%を占め、50歳以上では87.9%となり、経営者の高齢化が進んでいる。
なお、50歳以上の経営者で「後継者有り」は55.0%であるが、「後継者無し」の割合も40%を超え今後の課題といえる。
|
| (2) |
平均の営業時間は11時間 |
|
1日の営業時間を見ると、「12〜13時間未満」が31.3%で最も多く、次いで「11〜12時間未満」が30.5%で続き、平均では11.0時間である。開店時刻では「8時台」が58.4%と最も多く、閉店時刻は「19時台」が47.8%と最も多い。顧客ニーズに沿った対応であるが、早朝からの長時間営業となっている。
|
| (3) |
来店客数は立地によって大きな差 |
|
1日当たりの来店客数では、店舗の立地で大きな差がある。「オフィス街」立地では161.9人、「商業地」32.3人、「住宅地」30.6人、平均で37.2人である。商業地や住宅地に立地の場合、外交による営業の割合が50%を占め、営業形態に差異がある。
|
| (4) |
受注割合、「持込」「外交」で地域差
|
|
受注数の「持込」と「外交」の構成割合を見ると、「外交」は「関東・甲信越」68.7%、「九州」67.1%と高く、逆に「近畿」39.2%、「北海道」41.0%と低い。近畿では「取次店経由持込」45.7%、北海道では「直接店舗持込」44.0%の割合が高い。地域によって、営業形態に特徴が見られる。
|
| (5) |
経営上の問題点、第2位「原材料費の上昇」 |
|
経営上の問題点(複数回答)では、「客数の減少」が82.0%で最も多く、他の業界と差はないが、次いで「原材料費の上昇」68.5%、「客単価の減少」53.4%、「諸経費の上昇」41.8%と続く。クリーニング業界の特質として、溶剤や洗剤などの原価上昇が、収支面で負担となっていることが窺える。
|
|
|
3 「クリーニング業法」に定める規則等
「クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もってその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ること」を目的に、「クリーニング業法」が昭和25年7月に施行されている。
|
| (1) |
クリーニング業の定義 |
|
クリーニング業は「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯すること(繊維製品を使用するために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与して繰り返して行うことを含む。)を営業すること」と定義され、その対象物は衣類のみでなく、シーツ、毛布等の寝具類、カーテン、絨毯、床マット等のインテリア、化学雑巾、モップ等の清掃用品、飲食店への貸おしぼり等、サービスの範囲は多種多様である。
なお、クリーニング業としての行為は洗濯のみでなく、受取り、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡しなど一連の付帯行為が含まれる。これら行為の一部のみを行う場合にあっても対象となるが、原型のまま洗濯することが要件であり、着物の「洗い張り」は含まれない。
|
| (2) |
クリーニング所(クリーニングを行う施設) |
| |
営業者は、クリーニング所(洗濯物の受取及び引取のみを行うものを除く。)以外において、洗濯物の処理を行い、又は行わせてはならないとされている。また、洗濯に関する設備(機器や車両など)や洗濯物の取り扱い等に要件の規定がある。
さらに、クリーニング所の開設又は廃止には都道府県知事への届出が必要であり、開設には一人以上のクリーニング師を設置することとし、また、構造設備について都道府県知事の使用前検査確認を受けなければならない。
|
| (3) |
クリーニング師 |
|
クリーニング師免許は、中学校を卒業した者で、都道府県が行うクリーニング試験に合格した者に対し、都道府県知事が与える。なお、クリーニング師がクリーニング業に関して罰金刑以上の罪を犯した場合、都道府県知事は免許の取消ができる。
クリーニング師は、業務に従事後1年以内に都道府県知事が指定した研修を受ける必要があり、以降3年を超えない期間毎に所定の研修を受けなければならない。
|
| (4) |
業務従事者への講習等 |
|
営業者は、その業務に従事する従業者に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければならない。従業者5人に1人以上の割合で、開設後は1年以内に、以降3年を超えない期間毎に所定の講習を受ける必要がある。
都道府県知事は、営業者又は従事者に対して、伝染性の疾病でその就業が公衆衛生上不適当と認める時は、業務を停止することができる。
|
| (5) |
環境衛生監視員による検査 |
|
クリーニング所又は業務用車両について、クリーニング業法に定める衛生基準を遵守して運営しているか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は環境衛生監視員を設置し、当該監視員等から報告を求めることとしている。また、監視員は必要に応じて施設等への立入検査ができる。 |
| (6) |
営業停止処分等 |
|
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、営業者がクリーニング業法の定めに従わない時は、営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用車両の使用停止を命ずることができる。
営業所の廃止処分や免許の取消を行う場合、公開による聴聞会を開催する。
|
|
|
4 クリーニング業の業界よもやま
| (1) |
多様な営業形態 |
| |
クリーニング業は、主に衣類の洗濯等を代替サービスする営業であり、消費者は衣料や住環境において衛生的で快適な生活が維持され、家事労働時間が短縮されることになる。クリーニング業の営業形態は多様であり、分類すると以下のとおりとなる。 |
| ア |
普通クリーニング店 |
| |
クリーニングのための自家処理設備を持ち、主として家庭からの洗濯物をクリーニングする営業所であり、シロ物の水洗いランドリークリーニングとクロ物のドライクリーニングからなる。多くの店は双方を処理するが、小規模店ではシロ物を「ホールセール」へ外注委託するケースも増加している。
|
| イ |
リネンサプライ |
|
総務省・日本標準産業分類では「繊維製品を洗濯し、これを使用するために貸与し、使用後に回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行う」事業体と定義している。病院、旅館・ホテルが需要の主体であるが、事業所の作業服や飲食店の貸おしぼり等多岐にわたる。 |
| ウ |
ホールセール |
|
普通クリーニング店等から洗濯物を受注して専門的に処理する業者であり、ワイシャツなどシロ物の量的処理を主力とする。近年は、毛皮、皮革などの特定品目を取扱う業者も現れている。 |
| エ |
クリーニング取次店 |
|
クリーニングの自家設備を持たず、顧客とクリーニング業者の仲立ちとして、洗濯物の受取りと引渡しのみを行う店舗である。洗濯物を取り扱うことから、「クリーニング所」として一定の衛生水準の維持が義務付けられている。 |
| オ |
コインランドリー |
|
硬貨等投入式の自動洗濯機と乾燥機を設置し、顧客自身が設備を操作して洗濯するセルフサービス方式の店舗で、無人店舗の場合が多い。公衆浴場業の兼業として参入する他、郊外で駐車場を完備した大型施設も出現している。
|
| (2) |
クリーニング店利用の中核は「勤務者世帯」 |
|
総務省「家計調査年報」により世帯主の年齢階層別に「洗濯代」家計支出額を見ると、「50歳台」が11,125円と最も多く、「40歳台」「60歳台」が8,000円で続く。月平均では1千円未満であるが、ワイシャツなどを中心に勤務者世帯の需要が中核を担っているといえる。
|
| (3) |
機能高度化する家庭用洗濯機と洗剤 |
|
「漬け置き洗い」「浮かし洗い」「シャワー濯ぎ」など、デリケートな繊維素材や大型衣料に対応する機能を高度化した洗濯機が一般家庭に普及してきている。また、ドライクリーニング指定衣料が家庭で洗濯可能な洗剤も市販されており、これまでは専門店で処理してきたことが家庭でできるようになっている。これらの機材や洗剤によって、コインランドリーの機能拡大に波及しており、セルフランドリーチェーンの進出も見られる。
|
| (4) |
環境保全への対応 |
|
ドライクリーニングの溶剤としては、石油系溶剤とテトラクロロエチレンが使用されている。これらの溶剤は、健康被害や環境汚染を引き起こす可能性もあるため、適切な管理が必要であることから多数の規制がなされている。また、平成19年4月、改正容器包装リサイクル法が施行されており、ポリエチレン製包装袋への対応をどうするか、業界として喫緊の課題であり、溶剤等の問題と併せ対応が急がれる。
|
| (5) |
クリーニング・トラブル |
| |
「平成17年度経営実態調査(前述)」において、クリーニング・トラブルが調査されている。1ヶ月間に30%の店舗で、1店舗当たり2.1件発生していることになる。「取次店」においても1年間で70%の店舗で、1店舗当たり5.0件発生している。顧客側の責任の場合もあるが、トラブル解決は容易でない。対応を間違えると無用な信用失墜となり、口コミが災いする。
|
| (6) |
経営のポイント |
| |
洗濯機の高機能化、衣料品の素材革新など、市民生活は大きく変化してきており、クリーニング業界を取り巻く経営環境は厳しいものがある。厚生労働省「クリーニング業の実態と経営改善の方策」から、経営のポイントを探ってみたい。 |
| ア |
顧客ニーズに立ち返る |
| |
経営の原点に立ち返り、「顧客は何を求め、何を期待しているのか」を現場サイドで今一度、問い直してみることが重要である。 |
| イ |
経営コストを再点検する |
|
実態調査において、今後の経営方針として「顧客サービスの充実」「専門店化・高級店化」「広告宣伝の強化」「施設・設備の改装」を挙げる。背反する「諸経費の上昇」に直結する課題を如何にして克服するか。経営コストを洗い直し、事業の実態を謙虚に見つめ直すことは有効である。 |
| ウ |
「強み」を活かす |
|
パート従業員を主体とする大手企業チェーン取次店との差別化を図る必要がある。きめ細かなサービスと営業により、地域住民との対話の中から「強み」を発揮していくことであろう。 |
|
|
資料
1 総務省「事業所・企業統計調査」
2 総務省「家計調査年報」
3 厚生労働省「衛生行政報告例」
4 厚生労働省「クリーニング業の実態と経営改善の方策」平成18年10月
5 厚生労働省「平成17年度生活衛生関係営業経営実態調査(クリーニング業)」
6 全国生活衛生営業指導センター「生活衛生関係営業ハンドブック2008」
|