| (1) |
事業所数の推移 |
| |
総務省「事業所・企業統計調査」により公衆浴場事業所数を見ると、平成18年調査において、前回調査(平成16年)に対し93.7%となっており、依然として減少傾向に歯止めがかからない。
|
|
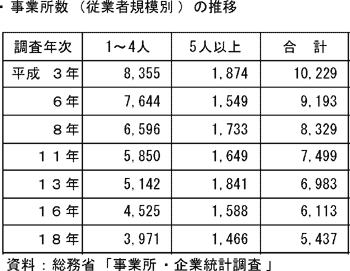 |
|
|
|
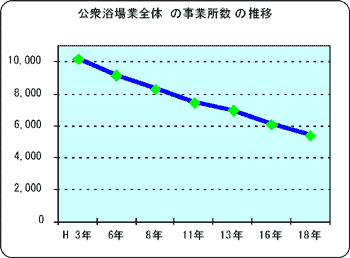 |
| (2) |
施設数の推移 |
|
厚生労働省「衛生行政報告例」による施設数を見ると、公営と私営の普通浴場を合計した「一般公衆浴場」は平成19年度末6,005施設となり、公衆浴場全体では施設数が増加している中で、一般公衆浴場、特に俗称「銭湯」(私営普通)の減少が著しい。
・施設数の推移
年 次 |
一般公衆浴場 |
ヘルスセンター |
サウナ風呂 |
公 営 |
私 営 |
計 |
昭和55年 |
524 |
15,172 |
15,696 |
593 |
2,378 |
60年 |
531 |
13,256 |
13,787 |
783 |
2,620 |
平成元年 |
504 |
11,724 |
12,228 |
1,061 |
2,934 |
5年 |
524 |
9,864 |
10,388 |
1,360 |
2,988 |
10年度 |
597 |
8,193 |
8,790 |
1,911 |
2,671 |
15年度 |
507 |
6,817 |
7,324 |
2,291 |
2,140 |
16年度 |
501 |
6,629 |
7,103 |
2,287 |
2,169 |
17年度 |
451 |
6,202 |
6,653 |
2,396 |
2,070 |
18年度 |
419 |
5,907 |
6,326 |
2,359 |
2,299 |
19年度 |
408 |
5,601 |
6,009 |
2,331 |
2,334 |
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」 |
| (3) |
営業許可件数、営業廃止件数の推移 |
| |
厚生労働省「衛生行政報告例」により、公衆浴場の営業許可と営業廃止の推移を見ると、営業許可(新規開設)は平成17〜18年度に増加したものの直近では減少しており、営業廃止は増加傾向が続いている。
・営業許可及び営業廃止件数の推移
調査年次 |
営業許可 |
営業廃止 |
昭和55年 |
1,439 |
1,577 |
60年 |
1,633 |
1,593 |
平成元年 |
1,232 |
1,158 |
5年 |
1,242 |
1,031 |
10年度 |
1,347 |
1,027 |
15年度 |
1,356 |
1,215 |
16年度 |
1,566 |
1,356 |
17年度 |
2,060 |
1,450 |
18年度 |
2,669 |
1,600 |
19年度 |
1,693 |
1,633 |
資料:厚生労働省「衛生行政報告例」 |
| (4) |
最近の業界動向 |
| ア |
鎮静化しない「銭湯」の廃業 |
| |
厚生労働省「衛生行政報告例」によると営業許可と営業廃止はほぼ同数のバランスで推移してきている。最近の傾向では、営業許可は一進一退であるのに対し、営業廃止は増加傾向にある。問題は、営業廃止の中核が一般公衆浴場業「銭湯」であって、公衆浴場業全体の構造変化が依然として進んでいることにある。
内風呂付住居は生活様式の構造的なものであり、これを主因とする公衆浴場「銭湯」入浴客数の減少は抗し難い。併せて、経営者の高齢化、燃料代の高騰等、経営環境の悪化が営業廃止に拍車をかけているのが現実である。 |
| イ |
地域の人的交流の場として開放 |
|
そもそも一般公衆浴場は、地域の市民生活の中で「人と人との裸の付き合い」の場を提供してきた。核家族化の進展等に見られるように、個々の繋がりが薄れるとともに地域社会の連携が希薄化してきた。これを見直す動きとして、「銭湯」を核とした人的交流の再生活動が生まれ、地域のイベント会場等で施設を開放する動きが見られる。
|
| ウ |
福祉入浴援助事業の進展 |
|
高齢化社会の進展は避けて通れない。また、その社会構造に即した事業活動や市民サービスが求められている。これを背景として、高齢者や身体に障害のある方が、容易かつ安全に入浴できるように「段差解消のためのスロープの設置」「浴槽やトイレ等、施設内への手すり設置」「滑りにくい床への改良」等、バリアフリー化を推進する公衆浴場施設が増加している。これらの改造に加え、介助を伴う入浴事業を「福祉入浴援助事業」として認定し、これを行う一般公衆浴場に対して固定資産税軽減措置が行われている。
|
|
|
2 一般公衆浴場の特性と現状
| 厚生労働省の委託により全国生活衛生営業指導センターが実施した「平成19年度生活衛生関係営業経営実態調査(公衆浴場業)」から、一般公衆浴場の現状を探ってみたい。 |
| (1) |
高齢化が進む経営者 |
|
経営者の年齢分布を階層別にみると、「70歳以上」が36.5%で最も多く、次いで「60歳台」33.4%、「50歳台」23.4%の順となっており、60歳以上で69.9%を占める。
後継者の有無を見ると「あり」は43.7%であるが、小規模な「個人経営」の場合の「後継者あり」は39.9%である。法人経営では若干「後継者あり」の構成割合が高くなっているものの、後継者の確保は喫緊の課題といえる。
|
| (2) |
小規模事業体が大半 |
|
従業者10人以上の割合が5%に過ぎず、4人以下が74.8%を占める。事業体の創業年次を見ると、80%が昭和元年〜49年であり、大正以前を加えると92%を超える。家族従業員を中心に、労働集約型の小規模経営で長い歴史を支えてきていることが伺える。
|
| (3) |
営業時間は8〜10時間、閉店は24時台 |
|
開店時刻は平日、休日ともに「14時から16時頃」に集中しており、営業時間は「8〜10時間」が大半を占める。必然的に閉店時刻は「23時台」が30%前後で最も多く、22時台〜24時台で75%を占め、深夜に及ぶ長時間営業の実態が浮かぶ。労働時間短縮努力の有無では「有り」が35.4%であり、就業規則の整備は全般に低い水準にあり、ここでも家族従業員中心の労働環境が垣間見える。
|
| (4) |
老朽化する建物設備
|
|
営業店舗の所有状況を見ると、「土地・建物とも自己所有」が79.3%と8割を占める。その建物の新築又は改築後の経過年数を見ると、「20〜39年」34.6%、「40年以上」48.4%であり、「50年以上」が26.0%と最も多く、老朽化が著しい。
|
| (5) |
浴槽の多様化 |
|
浴場設備のうち浴槽数は、「9槽以上」が32.9%と最も多く、次いで「5〜6槽」27.7%、「7〜8槽」22.9%となる。その種類を見ると、「気泡風呂」60.7%、「噴射風呂」55.8%、「超音波風呂」52.7%、「湯温度の異なる風呂」49.5%、「薬湯・温泉」46.9%、以下、「電気風呂」「季節風呂」の順となっている。また、サウナ設備を備えている割合は57.9%を占め、入浴設備でサービスの多様化が一般的になっている。
|
|
|
3 「公衆浴場法」等に定める規則等
公衆浴場は不特定の一般人が入浴することから、高度の衛生施設の維持・向上が求められ、昭和23年7月法律施行の「公衆浴場法」が定められている。この他、昭和21年3月施行の「物価統制令」によって入浴料金の統制を受けており、昭和56年6月施行の「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」が適用される。また、都道府県条例によって施設の配置規制があり、公衆浴場の維持に関する法規制が整備されている。
|
| (1) |
公衆浴場の定義 |
|
「公衆浴場法」において、公衆浴場は「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義され、都道府県知事の許可を受けて営業することとしている。 |
| (2) |
法の適用される施設の範囲 |
| |
営業許可の対象となる公衆浴場は「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に区分される。さらに、「公衆浴場法」の適用される施設と、他の法令や条例等に基づき運営され衛生措置の講じられる「公衆浴場法」適用外の施設とに分けられる。
|
| ア |
一般公衆浴場 |
|
地域住民の日常生活において、保健衛生上必要なものとして利用される施設であり、「物価統制令」によって入浴料金が統制されている私営の通称「銭湯」や公営の福祉センター等に併設される浴場施設がある。
|
| イ |
その他の公衆浴場 |
|
・保養や休養を目的とする「ヘルスセンター」「健康ランド」
・スポーツ施設(ゴルフ場、アスレチックジム等)に併設する浴場
・企業の福利厚生施設として設置された工場などの浴場
・健康や美容を目的とする「サウナ」「エステテイックサロン」
・介護や介助を目的とする「移動入浴車」「介助浴槽(デイサービス用を除く)」
|
| ウ |
公衆浴場法の許可対象としない浴場 |
|
・「労働安全衛生法」により工場、作業場に設置された浴場
・「労働基準法」により企業体付属施設としての寄宿舎の浴場
・「旅館業法」の適用を受ける宿泊施設の浴場
・「老人保健法」に基づく事業のみを行う施設(デイ・ケア)に設けられた浴場
・国や自治体が実施する介助を伴った入浴サービスに使用される浴場 |
| (3) |
営業の許可 |
|
業として公衆浴場を営業する者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があり、都道府県条例の定める構造設備基準、適正配置基準に準拠し、換気、採光、照明、保温及び清潔その他の衛生基準及び風紀基準に従うことが求められる。
営業者は伝染性疾病に罹病していると認められる者の入浴に対して、その入浴を拒まなければならないとしている。 |
| (4) |
環境衛生監視員による検査 |
|
公衆浴場を営業する場合、条例等に定める衛生基準を遵守して運営しているか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は環境衛生監視員を設置し、当該監視員等から報告を求めることとしている。また、監視員は必要に応じて施設等への立入検査ができる。 |
| (5) |
営業許可の取消及び営業停止命令 |
|
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、許可条件やその他規定に違反した営業者に対し、許可の取消又は営業停止を命ずることができる。ただし、許可の取消を行う場合、公開による聴聞会を開催する。 |
| (6) |
「物価統制令」による料金の統制 |
|
第2次世界大戦後の混乱期において物価高騰を抑制し、国民生活の安定を図ることを目的に「物価統制令」(昭和21年3月施行)が制定された。現在「一般公衆浴場」のみが、国民大衆の日常生活に必需であるとして、この法律の適用を受けている。
この法律に基づき都道府県知事は、審議会に諮問したうえ、その答申を受けて入浴料金の上限を「統制額」として指定する。 |
| (7) |
「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」 |
|
昭和56年6月、「物価統制令」の適用を受ける「一般公衆浴場」について、その著しい減少に歯止めをかけ、国民大衆の日常生活に支障とならないよう特別措置を講じ、利用機会の増進を図ることを目的に制定された。
国や自治体による助成や日本政策金融公庫の特別融資など、必要な措置を講ずるよう配慮することが盛り込まれている。 |
|
|
4 公衆浴場業の業界よもやま
| (1) |
一般公衆浴場「銭湯」創業者の出身地は北陸圏 |
| |
関東圏や近畿圏、北海道などでの「銭湯」創業者は、北陸4県(新潟、富山、石川、福井)出身者が多いという。特別な調査が行われた訳ではないが、関東・近畿等の公衆浴場業生活衛生同業組合役員には「北陸をルーツ」とする方が多い。北陸は、米作りを一毛作してきた経緯があり、水田は生活基盤を支える財産である。藩政時代に新田開発が終わり、田畑を長男一人に相続することで分散を防ぎ、次男以下は土地を離れることが必要となり、勤務先を求めて都市圏などに移住することになる。都市圏では既に人が溢れ、「公衆浴場業」や「豆腐製造業」など、長時間労働で営業時間の変則的な職種に就労して生計維持することが多かったという。勤勉で粘り強かったことから、徐々に経営者として独立していったものであり、更に血縁を頼って後継者が育成されていくことになる。 |
| (2) |
「銭湯を全く利用したことがない」50%超(東京都) |
|
東京都生活衛生営業指導センター「平成15年度消費者モニター等事業報告書」により東京都における「一般公衆浴場(銭湯)」の消費動向を見ると、「全く利用したことがない」が56.0%であり、過半数が利用経験すらない。「ほぼ毎日」利用が6.5%にすぎず、「風呂なし賃貸住宅」は過去のものとなり「神田川」の世界は消滅していく。
|
| (3) |
経営のポイント |
|
東京都生活衛生営業指導センター「平成15年度消費者モニター等事業報告書」において、公衆浴場を利用する際の意識調査(複数回答)がされている。「リラックスできる」59.3%、「広々している」58.3%、「疲労回復できる」56.2%、「清潔感がある」47.9%、「いろいろな浴槽がある」37.0%、「自宅や職場から近い」32.9%の順となっており、利便性よりも、公衆浴場の持つ心理的側面に満足度を求めていることが分かる。
経営環境の厳しさに押し潰されては何も生まれない。公衆浴場に求める意味を再認識し、入浴好きな日本の市民生活に存在意義を発揮するための挑戦が期待される。厚生労働省「公衆浴場業の実態と経営改善の方策」から、経営のポイントを探ってみたい。
|
| ア |
公衆浴場に求める顧客ニーズの再認識 |
| |
顧客の意識が「リラクゼーション」にあることを再認識し、的確な対応を展開する。 |
| イ |
健康入浴の推進 |
|
健康入浴推進事業に対応し、地域住民の健康増進・福祉の向上を目指す。 |
| ウ |
高齢者や障害のある方への福祉入浴援助 |
|
福祉入浴援助事業に対応し、経営面での方針を明確にする。 |
| エ |
地域の核として市民との共生 |
|
地域住民の相互対話の場として、共生を追求する。 |
|
|
資料
1 総務省「事業所・企業統計調査」
2 総務省「家計調査年報」
3 厚生労働省「衛生行政報告例」
4 厚生労働省「公衆浴場業の実態と経営改善の方策」平成21年1月
5 厚生労働省「平成19年度生活衛生関係営業経営実態調査(公衆浴場業)」
6 全国生活衛生営業指導センター「生活衛生関係営業ハンドブック2008」
7 東京都生活衛生営業指導センター「平成15年度消費者モニター等事業調査報告書」
|